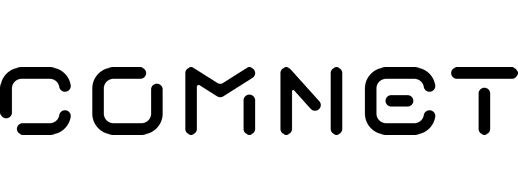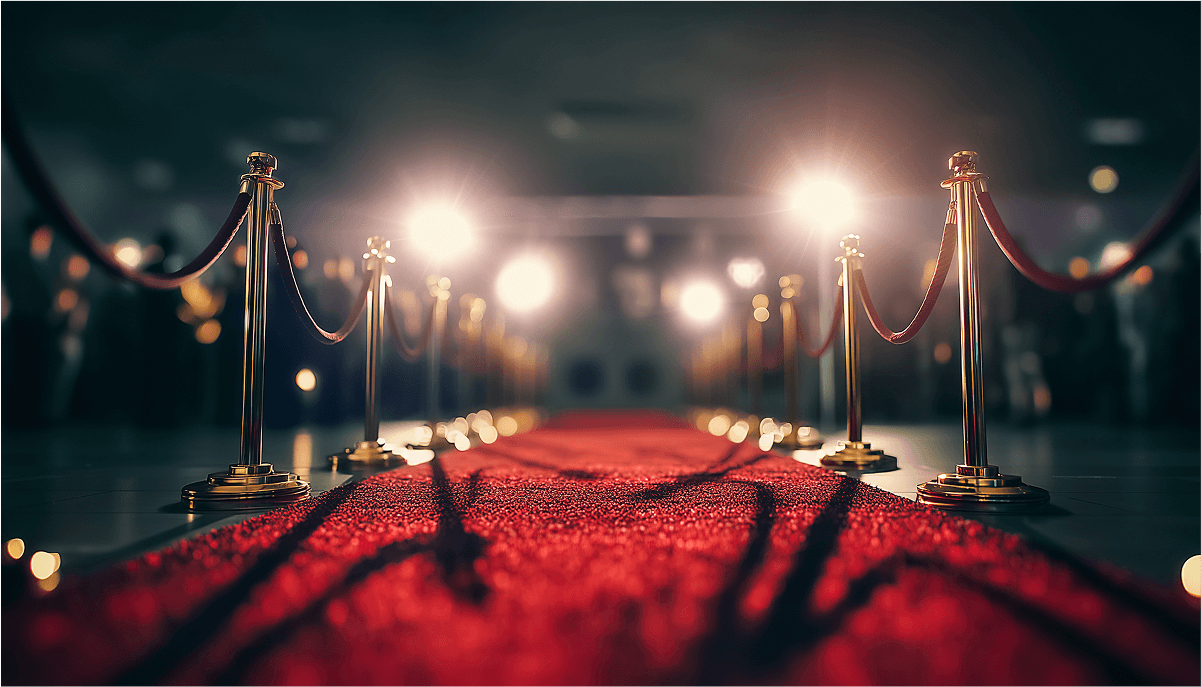仕事に対するモチベーションのあり方は、生産性を大きく左右します。モチベーションを高めるために多くの会社では上司からの「褒める」「叱る」といった働きかけや、報酬の提示などの動機づけを行っていますが、成果が上がっている会社ばかりではありません。
ここで取り入れてもらいたい手法に、モチベーションスキルの学習があります。
いうまでもないことですが、会社は個々の社員の集合体です。多くの社員がモチベーションを自由にアップさせることができれば、会社全体の業績アップにもつながってくるはず。ここでは、「モチベーションスキル」がどういったものなのか、その概要をご紹介していきます。
モチベーションの安定こそが生産性向上の近道
年末年始やゴールデンウイークなどの長い休み明けに、モチベーションが低下してしまい、辛かった…そんな経験を持つ人は多いと思います。「プライベートで気になることがあると、なかなかモチベーションが上がらない…」という人もいるでしょう。
逆にモチベーションが高いときには仕事の効率が一気に上がり、短時間で大きな成果を上げられる状態になります。常にこの状態が維持できれば、スタッフ一人に対する業務量の設定も変わってくるでしょう。それが、ひいては会社全体の生産性の向上にもつながることになります。
逆に、モチベーションの波が大きいと、業務量の設定が難しくなります。
「モチベーションには波があって当たり前」と思われるかもしれませんが、一定のスキルを身につければ、ある程度のコントロールが可能になります。モチベーションを安定させることが、生産性向上の近道につながるのです。
モチベーション・クライシスとは?
今の日本の若者には、「仕事に対してやる気が出ない」「なぜ頑張らないといけないか理解できない」という人が多いといわれています。その状態は「モチベーション・クライシス(働く意欲の危機)」と呼ばれ、近年社会問題化してきました。ニートやフリーターの増加も、この要因が大きいといわれています。
もしかすると、会社で採用した新入社員の中にも、モチベーションが感じられない人がいるかもしれません。この要因のひとつが、終身雇用制度の崩壊によって企業への貢献意義を見失っていることだといわれています。「会社のために身を粉にして働いても、いつまで雇ってもらえるかわからないから意味がない」という考え方に陥ってしまうのです。
もちろんモチベーション・クライシスにはそのほかにも、労働形態の多様化や情報量の拡大などさまざまな要因が関係しています。これらを解消するには、終身雇用に代わるモチベーションを社員に呈示することが必要になります。
「モチベーションスキル」を高めよう
「モチベーションスキル」という考え方では、モチベーションを心理学や神経学、行動科学などの側面から科学的にとらえます。たとえば、同じ「掃除」という行動に対し、「面倒だ」と感じる人はあまり掃除をしません。「掃除をすると気持ちが良い」と考える人は、積極的に掃除します。「気持ちが良い」という快感がモチベーションになるわけです。
モチベーションスキルのアップは、次のようなステップで進めていきます。
- 取り組みの理由を明確化する(この範囲の石を拾って⇒× 野菜を植えるために石を拾って⇒〇)
- 取り組みへの動機をイメージする(自家製の美味しい野菜でスープを作るイメージなど)
- 過程を楽しめる工夫をする
- 毎日の行動・取り組みに対して意味づけする(水やり、草むしり⇒「美味しい野菜を育てるため」という目標を思い出す)
- 行動を邪魔する要因を取り除く((畑が広くて)(暑くて)草むしりが面倒→1日の作業面積を全体の3分の1にする、作業時間を早朝や夕方にずらす、など)
- 感情を良好な状態で維持する
社員が賛同し協力したいと思える会社の方針があれば、それが仕事に対するモチベーションの根幹となるはず。そうでなければ、方針をいくら説明してもモチベーションにはつながりません。業績目標だけを追求するのではなく、セルフコントロール可能な行動目標を提示し、チャレンジ目標は別に設定することで成長をサポートしましょう。
社員がモチベーションを保つための教育を
プロとして仕事をするうえで、モチベーションを一定に維持し、生産性を確保することは大切なことです。しかし、多くの人がその方法を理解できていないため、実行するに至っていません。
社員にモチベーションスキル教育をすることで、生産性の確保を図ることができれば、競合他社から一歩抜きんでることができるかもしれません。この機会に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか?